今回は油絵用、テンペラ用の下地の
石膏地と白亜地について解説します。
目次
「石膏地」「白亜地」とは?

西洋絵画では古くから
板絵の下地として使われていたのが
石膏地と白亜地です。
おもにイタリアでは石膏地が使われ、
ドイツやベルギーでは白亜地
が使われていました。
これらの下地は、油絵具の油分や
テンペラ絵具の水分を吸収するので
吸収性下地と言われます。
絵の具の定着が良く乾くのも早い
という利点があります。
また石膏地、白亜地作りは
自作した石膏液を薄く何層も重ねて厚みを出していきますので
かなりの手間と時間が掛かります。
ですので、私は新しい絵を描く度に毎回下地を作るのではなく、
ある時期に、まとめて一気に作ってしまいます。
初夏と秋のころに、「下地作りの日」というのを
スケジュールに入れておき、数日かけて10枚以上作り、
これを半年くらいで使うようにしています。
石膏液をパネルに塗るときには、気泡ができないように薄く重ねて、
これを最低でも5層は塗ります。
黄金背景の石膏地の場合は10~15層重ねて、
最終的に鋼板で研磨をしてフラットな画面を作ります。
いずれもキャンバスなどの柔軟性のある支持体に塗ると
ヒビが入る可能性が高いので、
木製パネルなどの固いものに向いている塗料です。
石膏
石膏は硫酸カルシウムを主成分とした鉱物で
水と混ぜると固まります。
美術・工芸、医療、建築・土木、農業など
幅広い分野で使われていて
「焼石膏」と呼ばれます。
身近なものでは、ギプスや歯科治療でも
使われています。
絵画の下地用に使われる石膏は
おもにイタリア産の
「ボローニャ石膏」でしょう。
ボローニャ石膏は軟質で
固めたあとでも多少の弾力性が残るので
金箔を貼って磨いたり
装飾をしたりする際に有利です。
イタリアでは安値で売っていますが、
日本で販売しているものは輸入品なので
少々お高めです。
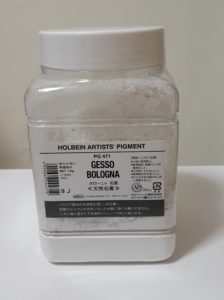
ボローニャ石膏 1㎏約¥3,500
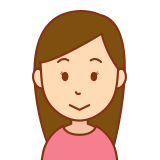
ちなみに石膏、白亜のことを芸術用語では体質顔料といいます♪
白亜
白亜は、おもに貝やサンゴ、
微生物などの死骸が化石化した
「炭酸カルシウム」で出来ています。
スペインやフランス、
ベルギーなどの山岳地帯で
産出される天然白亜です。
画材用の白亜には2種類あります。
●ムードン(フランス産)
●スペイン白(スペイン産)
画材屋さんでは
下地用と仕上げ用に分けて売られている物もあります。
この違いは何かというと
単純に好みの問題かと思います。
それぞれを私が使った感想では
下地用は、膠と混ぜて塗った時に
薄いベージュっぽい色。
仕上げ用の方は白い。
どちらかといえば仕上げ用の方が粒子が細かい、
という印象でした。
あらかじめムードンに粉のチタニウムホワイトを混ぜておくことで
ベージュではなく白い下地を作ることも出来ます。
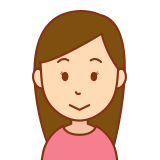
白亜地は石膏地に比べるとかなり硬い表面になるので、厚塗りをすると割れてしまいます。塗り重ねは3層くらいで大丈夫です。
石膏地パネルの制作
ではここからは 実際に石膏地パネルの作り方を解説していきます。
手順は以下の通りです。
(一日ではできないので数日に分けて作業をすることになります)
1、前膠用の膠液を作る
2、前膠
3、綿布を貼る
4、石膏液を作る
5、石膏液をパネルに塗布
6、表面を磨く
前膠用の膠液を作る
膠と水の量は 1:10くらい
①ビーカーに膠と水を入れてよくかき混ぜて
一晩置き、膨潤させておく。

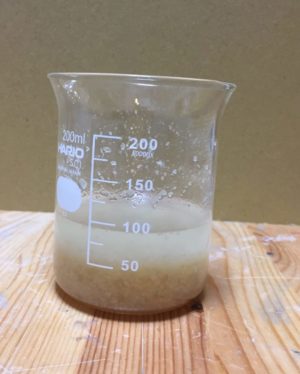
一晩置いたもの↑ 膠がふやけている
②翌朝、湯せんにかけて膠を完全に溶かす。

※湯せんの温度は60℃
画像は鍋底に直接ビーカーを置かずにタオルを沈めています
※前膠用に、適当な量を別のビーカーに取り分ける。
残った膠液は冷ましてから冷蔵庫保存。
膠液は冷蔵庫で約5日間保存可。
前膠
①支持体の下準備としてパネル全体に膠液を塗る。
(板が反ったりヤニが出たりするのを防ぐため)
温かい膠をパネルの表面、側面、裏面にも塗る。
パネルの裏面に画びょうを付けたり、画像のような
猫除け(ダイソー)を敷いて
地面から浮かせて作業をするとくっつかなくて良いです。

全体に塗れたら1日乾燥させる。
綿布を貼る
①綿布を準備。
綿布をパネルよりも5センチほど大きくカットする。
②乾いたパネルの表面に温かい膠を塗り、

膠が温かいうちに綿布を貼り付けて
さらにその上から膠を重ね、ゴムベラや手を使って
布目を埋めるようにしっかりと塗り込む。
側面、裏面へと貼っていく。
【ポイント】膠はいつも温かく冷まさないこと。
③綿布の端の処理
側面をきれいに織り込むため綿布に切り込みを入れる。

側面にも膠を塗りながら綿布を織り込む。

裏面まで貼り終えたら2、3日乾燥させる。
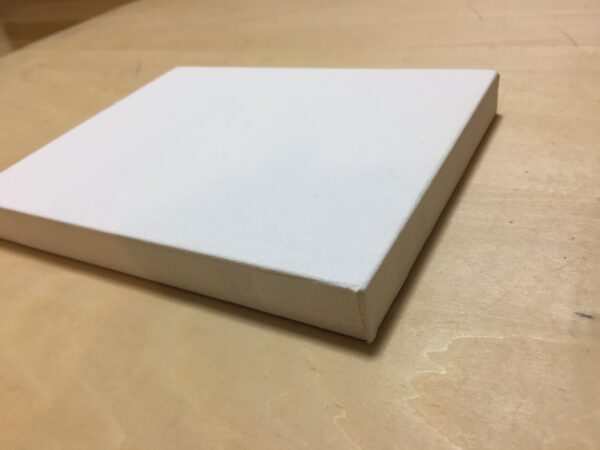

石膏液を作る
●支持体…
木製パネル、綿布(麻布、寒冷紗などでも可)
●膠…兎膠(トタン)
●ボローニャ石膏または白亜
ビーカー 湯せん器 ボウル
刷毛(筆) 計り ゴムベラ
ガラス棒 温度計 紙やすり など
①石膏用の膠水を用意
膠:水=1:10
前日から水に入れてふやかしておき
翌朝、湯煎にかけて溶かす。

②温かい膠液に石膏(白亜)を入れる。
茶こしなどを使ってダマにならないようにする。

少量づつ何回かに分けて入れる。
石膏(白亜)はゆっくりと沈んでいくので
沈んでは入れる、を繰り返す。
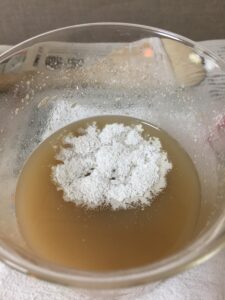


途中でかき混ぜない。
膠が冷めないように時々湯煎する。
③8分目くらいまで入れる。

④気泡が出来ないように一定方向にゆっくりと混ぜる。

石膏液の出来上がり。
一度撹拌したものに、石膏を加えない。
パネルに塗る
① 温かい石膏液を、布を貼ったパネルに塗る。
(この画像では寒冷紗を使用しています)
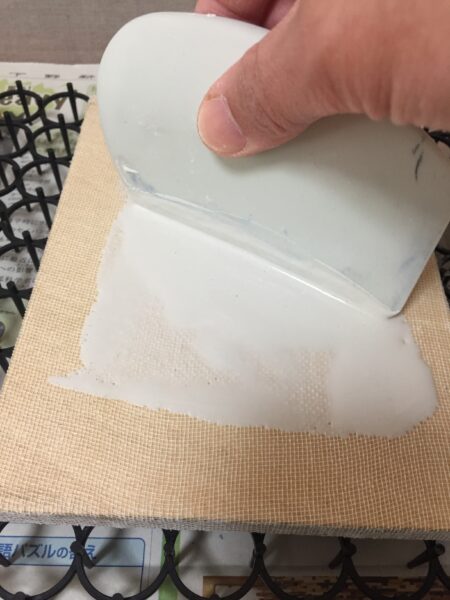
1層目は、寒冷紗の目を埋めるように
すりこむように
ゴムベラなどを使って塗る。
② 乾くのを待たずにすぐに2層目を重ねる。

2層目を塗ったら少しの間置いて
半乾きになったら3層目を塗る。
※石膏を乗せるタイミングは、
前の層が半乾き(濡れ色が消えてから)の状態で塗る。
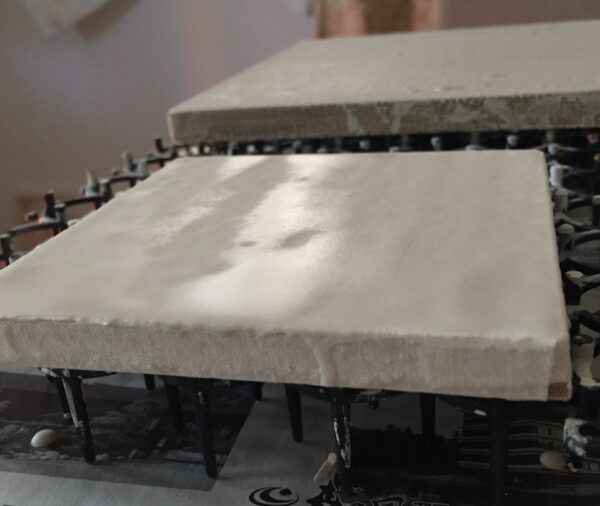
これを何層か重ねる。
油彩で絵を描くなら最低でも5層、
白亜なら3層、
黄金背景で金箔を貼る場合は15層くらいは塗る。
余った石膏液は冷蔵庫で約10日間保存可。
冷えて固まっても湯煎して使える。
表面を磨く
石膏を塗り終わったら、紙ヤスリを使って
表面を平滑になるように磨いて完成。
鏡面仕上げをするなら、鋼板で削ってから
紙やすりで整えます。
鋼板を使った削り方は
石膏地を作る制作過程 ←こちらの記事にも載せています。
まとめ
今回は石膏地と白亜地についてご紹介しました。
この下地剤を作るのは
時間と手間がかかる大変な作業ですが
ときにはちょっとこだわって
古い時代の技法を紐解きながら
じっくりと作業をしてみる…
なんていうのも良いのではないでしょうか。
普通の下地剤(ジェッソ)については
コチラの記事で解説しております。
合わせてご覧ください♪


